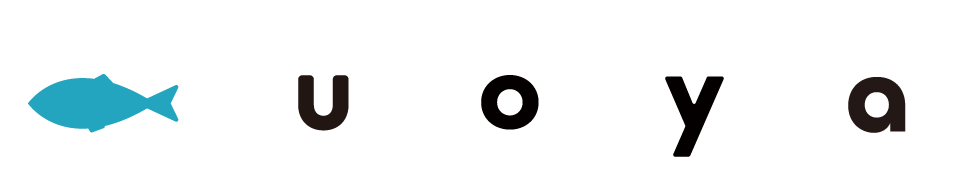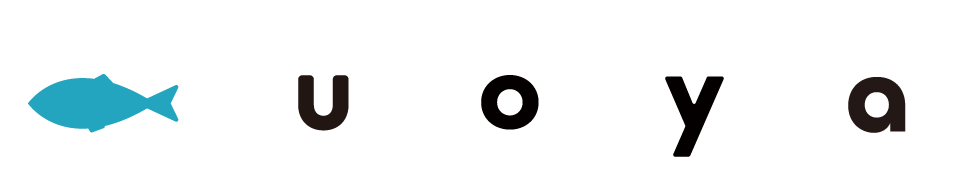生魚を超える?冷凍技術の最前線
「冷凍の魚は鮮度が落ちる」という常識が、最新技術によって覆りつつあります。従来は凍結時に細胞が破壊され、解凍時に旨味や水分が流出する課題がありましたが、近年の急速冷凍技術の進化により、生魚同様の食感と風味を保ったまま保存できるようになりました。例えばプロトン凍結は磁力や冷風を駆使し、一気に魚を凍結することで氷の結晶を極小化し、細胞破壊を防ぐ手法です。品質劣化の早い生シラスなども獲れたての状態で冷凍保存でき、解凍後も本来の美味しさが楽しめるといいます。またCAS凍結(セル・アライブ・システム)では特殊な振動を与えて氷結晶の成長を抑え、解凍時のドリップ流出を最小限に抑えることに成功しました。この技術は刺身用マグロなど高級魚の冷凍に活用され、世界中に日本の新鮮な魚を届けることを可能にしています。最新型の急速凍結機を用いれば、生鮮品を超える品質(味・鮮度)を実現した冷凍魚を製造することも可能だとされ、「生よりおいしい冷凍魚」の登場も現実味を帯びています。
都市の食卓に鮮度革命
こうした冷凍技術の進歩は、鮮度を妥協せず魚を取り入れる新たな手段として都市生活者に恩恵をもたらしています。遠隔地からでも品質を落とさず輸送できる冷凍魚は、流通の課題を解決し、都会でも安定して美味しい魚を楽しめる道を開きました。実際、トラックドライバーの労働規制強化による物流の2024年問題が取り沙汰される中、生魚輸送の制約を補う手段として冷凍技術への期待が高まっています。冷凍時の品質保証が整えば、生魚に匹敵どころか「生よりおいしい冷凍魚」を作ることさえ可能になり、生産者と消費者双方にメリットをもたらすと指摘されています。
こうした流れを受け、身近な小売の現場でも鮮度革命が起きています。例えばコンビニ大手のローソンは、2022年に真鯛とカンパチの冷凍刺身を発売し話題となりました。新型コロナ禍でまとめ買い志向が強まり「長期間保存でき好きな時に手軽に食べられる冷凍食品」のニーズが高まったことが背景で、関東・近畿からスタートした冷凍刺身の販売は全国約3000店舗へと拡大しました。刺身はすべて手切りで適切な厚みにスライスされ、真空パックごと流水解凍すれば数分で食卓に並びます。この商品開発には100 を超える試作が重ねられ、横浜の機械メーカーが開発した「凍眠(とうみん)」という-30℃の液体冷媒による急速冷凍技術が用いられています。特殊冷凍で旨味と食感を閉じ込めた刺身パックの登場により、都市の家庭でもいつでも手軽にプロ顔負けの刺身を味わえるようになったのです。