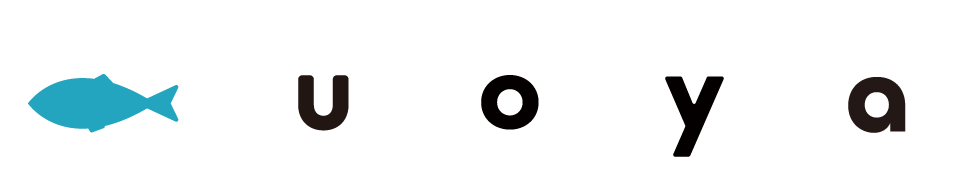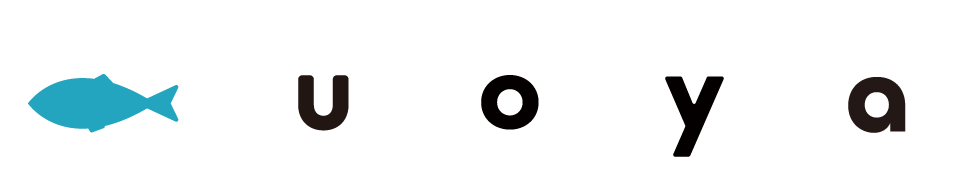蒲鉾づくりのはじまり
福島県いわき市の海沿いには、勿来・小名浜・永崎・豊間・薄磯・四倉・久之浜という七つの浜が続き、「いわき七浜」と呼ばれ、そこには海とともに暮らしてきた人々の営みがあります。薄磯海岸で白い砂浜を眺めながら、「前の工場はすぐそこだったんです」と話すのは、丸貞蒲鉾合資会社の小野英教さん。創業は昭和43年。お父様の小野貞夫さんは、親戚の水産加工会社で修業を積み、暖簾分けの形で独立しました。冷蔵技術がまだ発達していなかった時代、素潜りで魚を獲り、涼しい季節に加工する――そんな“海そのもの”の暮らしの延長線上に生まれた会社でした。当時は、「ウニの貝焼き」(ホッキ貝の殻にウニの身を詰めて蒸し焼きにした郷土料理)が有名で、素潜り漁を行う人も多かったのだそう。保存技術の進化とともに会社も成長、やがて蒲鉾を主力とする会社として、小野さんへと受け継がれていきました。
小さくていい。また始めよう。
小さくていい。また始めよう。
2011年、東日本大震災。突然の揺れに襲われ、家族は工場2階の住居へ避難。頑丈な鉄筋の建物に救われたものの、工場は操業不能に。避難生活を送りながら「もう一度やるのか、それとも終わりにするのか」と幾度も話し合ったといいます。そんなとき、長年の卸先から届いた「待ってるよ!」のひと言が、小野さんたちの背中を押しました。「小さくていい。また始めよう」。そう決めた瞬間から、家族の時間は再び動き出しました。
避難先の千葉から戻ると、空き工場を探し、機械をかき集め、片付けと再建に奔走しました。大学生だった次男の達哉さんも、長期休暇になると戻って掃除や廃材の搬出を手伝い、茨城まで何往復も。「あの頃がいちばん働きましたね」と小野さんは笑いますが、年末商戦に間に合わせるための必死の作業でした。蒲鉾・伊達巻を主力とする丸貞蒲鉾合資会社にとって年末の商機を逃すわけにはいかない、と急ピッチで移転の手続きや機械の手配に当たりました。「被害に遭って廃業された方も多く、使える機械を集めて・・ある意味託されたわけで、簡単にやめるわけにはいかないんです。」と話す小野さん。
今、丸貞蒲鉾の味を支えているのは、小野さん兄弟と達哉さんを中心とした“家族のチーム”。事務所には先代・貞夫さんが撮った海の写真が飾られています。「おじいちゃん、写真はプロ級だったんですよ。こだわりが強すぎて撮影が全然終わらないくらい」と達哉さんが笑う。レンズに残された海の景色は、家業の記憶そのもの。社名に刻まれた“貞”の字とともに、三代にわたる物語が静かに受け継がれています。
変わらない味、受け継がれるもの
看板商品の蒲鉾や伊達巻は、昔ながらの「むし蒲」。つなぎを極力使わず、魚本来の旨みをまっすぐ引き出すのが丸貞の流儀です。「まず自分たちがおいしいと思えるものじゃないと売れないんです」と小野さんは言います。揚げ物は地元の食卓を支える“日常の味”。一方で蒲鉾や伊達巻は、お正月やハレの日に欠かせない“節目の味”。その両方を支えてきたのが丸貞の歴史です。最近では、金頭や青さ、椎茸など、いわきの素材を生かした新しい挑戦も。「地元のものを使って、美味しいって言ってもらえるのが一番嬉しいですね」。そう語る口調には、味づくりへの迷いのなさと、静かな情熱が宿ります。
販売できないものを従業員が喜んで持って帰ってくれるときも、“ああ、ちゃんとできたんだな”って思います。
「やっぱり、お客さまに“おいしいね”と言ってもらえたときが一番です」。小野さんがそう語る姿には、丸貞が長く守り続けてきた“ものづくりの芯”がそのままあらわれています。事務所には、先代が撮影したいわきの海の写真が並びます。こだわりの強い、でも誰より海を愛した人の目線で写された風景。その写真と、社名に刻まれた「貞」の一文字が、三世代にわたって紡がれてきた物語を静かに語ります。震災を越え、家族で立ち上げ、今日も変わらず続いていく丸貞蒲鉾の味。その一品には、いわきの海と人の営み、そして“つくり続ける覚悟”がそっと息づいています。