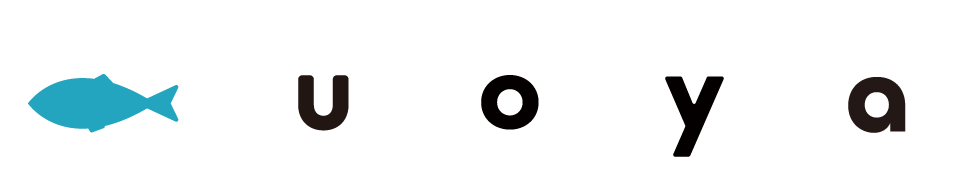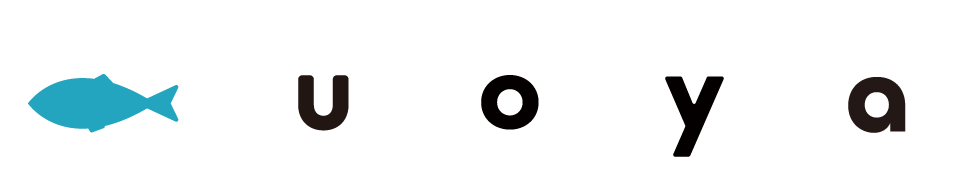失った場所から、相馬の味をもう一度
㊅佐藤水産は、福島県相馬市・原釜漁港の前浜に揚がる真蛸、やなぎ蛸、しらす、ちりめん、あおさなどを、その日のうちに加工して届ける水産加工会社です。看板の前で「亡くなった会長(祖父)が書いたものです」と話してくれたのは、専務の佐藤智紀さん。大学時代から家業を手伝い、やがて会社の中枢を担うようになります。結婚して間もない頃、東日本大震災が起こりました。
もう本当に、終わりだって感じでした。
でも、止まったら戻れないと思ったんです。
工場も住まいも失い、原発事故の報を聞いたあと、家族は山形、新潟、福井へと移動。取引先が手配してくれたホテルを転々としました。やがて兵庫県で住居の支援を受け、車3台で神戸へ向かいます。しかし生活が落ち着く前に、今度は長崎へ。震災前から縁のあった加工拠点で、夏に獲れる真蛸を加工し、出荷をつなぐためでした。神戸に家族を残し、父と義兄、そして佐藤さんの男3人で工場に入り、約1年にわたって“別の土地での仕事”を続けます。戻る場所がないまま、それでも仕事だけは止めなかった。再開の軸だけは失わなかった——その語りから、当時の張り詰めた空気が伝わってきました。
やり直すための「順番」があった
やがて相馬の市場復興が少しずつ動き出します。漁師から「やる奴いるか?」と声がかかり、親子会議になりました。社長(父)はどう思っているのか。迷いの中で返ってきた言葉は、短く、強いものでした。
俺は、やりたい。
その一言で工場再建に向けて動き出します。再建の鍵になったのは、「何を最初に揃えるか」という順番でした。社長が最優先したのは、しらすの乾燥機。タコのボイルは他所の設備を借りられる可能性がある一方で、乾燥だけは代替がきかない。「しらすが揚がっても、乾燥できなければ商品にならない」。相馬市でこの設備を持つ加工場は限られているからこそ、まずそこに投資したのです。
生のしらすは弱い。
新鮮なうちに一気にやらないと、折れるんですよ。
工場に入ると、その思想がそのままラインになっています。原料のしらすは水と一緒にロータリー槽を回り、流れるプールのような大きな槽へ。90度前後の温度帯で加熱され、6段の乾燥機を抜けていきます。天日やセイロで2〜3日かかっていた工程が、30〜40分で「カリッとしたちりめん」になる。仕上げに風力選別機で微小な異物まで飛ばし、品位を整えます。鮮度が落ちるとしらすは折れ、崩れ、見栄えが変わり、値段が落ちる。だから「当日、硬いうちに一気に仕上げる」。この工場は、そのためにあります。
ふんわり炊く「相馬流」を、次の定番へ
主力のひとつが、あおさ(海苔)の佃煮です。鍋で炊くのは半日、そこから冷やし、翌日に詰める。そうした手間をかけた製法で作られています。印象的なのは、ラベルや価格を大きく変えずに、売上が右肩上がりを続けていることです。派手なリニューアルで跳ねたのではなく、「変えない」ことで積み上がっていく伸び方。買った人が、また買う。食べ終えたら、もう一度手が伸びる。そういう増え方をしていました。派手さではなく、地力で選ばれている味です。
そして今、その佃煮の調味を起点に、新商品「しらす佃煮」を立ち上げています。市販の調味駅を買って味を研究し、ピンとくるものがなければ配合を組み替え、社長のGOが出るまで製品化しない。味はほぼ決まり、最後は色味の設計。白醤油を使って魚の表情を残すか、黒醤油で“佃煮らしさ”を強くするか。唐辛子は雰囲気程度にして、まず味を確かめる。瓶詰め後は温度を管理しながら殺菌して真空にし、常温で一年持たせることも視野に検査中です。佐藤さんは試食しながら「卵かけご飯にのせるのが一番」と笑っていました。相馬流の佃煮は、関西の釘煮のように固く煮詰めるのではなく、ふんわり仕上げる。その柔らかさが、ちゃんと土地の味として残っています。
この会社で、ここまで選別できるのは多分、自分だけです。
さらに印象的だったのは、買い付けの“目”です。しらすを買ったら、佐藤さんは一人で10種類ほどに選別すると言います。大中小、白・赤みの混ざり、色目や見栄え。混ざれば汚く見える。だから同質ロットで炊けるように分ける。見栄えで値段が決まる世界で、「これなら買うよね」というお客さん目線を、現場の手前で実現する仕事です。
魚を丸ごと買って家でさばく人が減るいま、佐藤さんは将来、鮮魚1:加工9の比率を目指すと言います。魚が不安定だからこそ、確保し、加工し、必要なときに届けられる形にする。相馬の漁師たちとも毎週の会議で情報を共有し、「何が高い? 何を獲ってくる?」という対話を続けている。漁師と加工は対等で、どちらが欠けても成り立たない。そのバランスの上に、“相馬の味”が次の定番へ育っていきます。