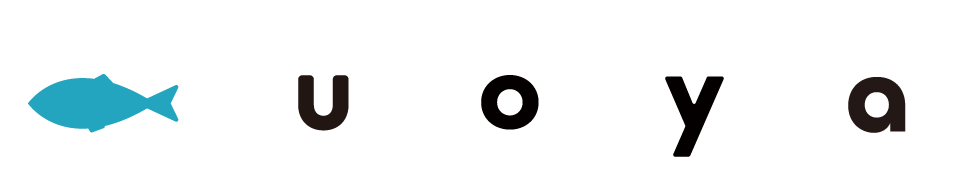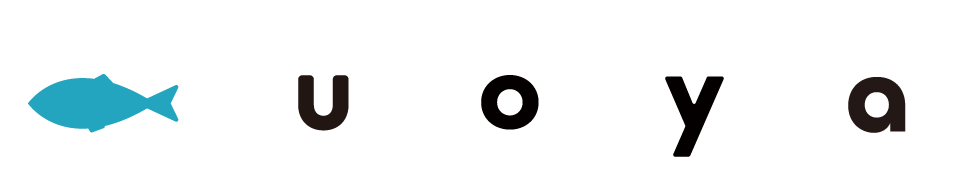全国でも希少な、あおさだけの工場
福島県相馬市・松川浦。潮の香りが日常に溶けているこの土地で、あおさ(ヒトエグサ)だけを見つめ続けてきた工場があります。株式会社マルリフーズ。扱うのは、海の畑から上がった“そのまま”のあおさです。小さなエビ、砂、他の藻類。自然界のものなんだから混じるのは当たり前——この浜では長く、そういう感覚で回ってきました。
自然界のものなんだから当然…これは東京じゃ通じない。
その「当たり前」を、いちばん強く疑ったのが、社長の稲村利公さんでした。18歳で相馬を離れ、東京で25年。銀行員から不動産業へ。海藻とは真逆の世界にいた人が、家業を継ぐことになって戻ってきたとき、最初に感じたのは違和感だったと言います。「自然のものだし、取ればいいだろう」——その理屈は浜では通っても、東京では通らない。厳しい目線を知ってしまったからこそ、稲村さんは“混じる前提”を“混ぜない前提”に変える決心をします。あおさに特化し、洗浄と異物除去を徹底的に突き詰める。ここから、マルリフーズの長い改造が始まりました。
震災で全壊しても、ラインは止めなかった
市場に認められはじめた矢先、東日本大震災が起きます。工場は全壊。津波は、事務所の天井近くまで来た。「止まったかも、と思ったところで止まった」。稲村さんは淡々とそう言います。けれど、その一言の裏にあるのは、言葉にしきれない恐怖と現実です。
1年後に工場を再建しても、今度は原料のあおさが入らない。仕入れ先を求めて全国を回り、交渉しても「福島だから」でひっくり返る商談が続く。展示会で“機械化して、異物をここまで減らしている”と説明しても、県名だけでシャッターを下ろされる。風評は、技術では折れない壁でした。
それでも稲村さんは順番を踏みました。狙うのは、基準がうるさい大手。少しでも異物があれば回収になる世界だからこそ、徹底的に選別された原料に価値が出る。異物選別を機械化し、独自の洗浄・異物除去ラインを組み上げる。海藻特有のにおいを抑え、香りを立たせる。地味で、終わりのない改善の積み重ねの先に、大手外食の採用が決まり、収益が安定していきます。
「あおさ=味噌汁」を壊しにいく
あおさの概念を崩す商品を作りたい。
ところが、コロナ禍。地震、大雨、水道停止。何度も“止まる理由”がやってきます。さらに原料不足。業務用の原料出荷だけでは踏ん張れない——そこで生まれたのが、発想の転換でした。「技術がすごい」と言っても伝わらない。だったら、まず“食べ方”を変える。若い人や女性に届く入口を作る。
こうして誕生したのが、常温保存できる万能調味料「松川浦かけるあおさ」。ご飯だけじゃない。パンにも、パスタにも、冷奴にも。味噌汁の脇役だったあおさを、主役として前に出す。名前の「かける」には、トッピングの意味と、「松川浦 × あおさ」を掛け合わせる意味が込められています。商品は“売るため”だけじゃなく、この土地の未来に火をつけるための言葉でもありました。
地元相馬へ。次の担い手を生むために
松川浦では高齢化と後継者不足が進み、廃業のスピードが継ぐスピードを上回っています。「この土地に由来のある商品が全国に広がれば、俺が継ぐ!って言ってくれる若者が出てくるかもしれないですからね。」そう話すのは営業部長の阿部純也さん。商品を広げることは、松川浦の“仕事の未来”を広げることでもあります。
「すてっぱず」は浜言葉で、「ものすごい」って意味。
2020年には地元企業や生産者と「すてっぱず松川浦」を立ち上げ、松川浦の逸品にロゴを付けて送り出す仕組みも作りました。震災、原発、コロナ、災害——折られても、また立ち上がる。その反復の中で、マルリフーズは“世界一のあおさ工場”を、松川浦の片隅に本気で作り続けています。小さな土地の小さな海藻が、海の外へ出ていく。その先に、この場所の次の担い手が立ち上がることを信じながら。