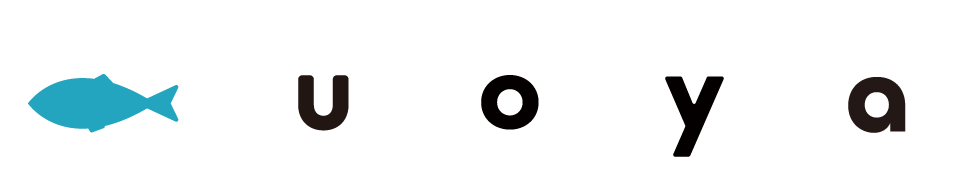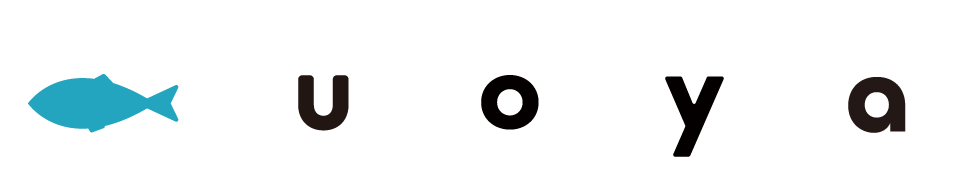漁師から干物屋へ
福島県いわき市の海沿いで3代続くカネキュウ鈴木商店。創業者は鈴木貴夫さんのおじいさんで、漁師をしながら加工も手がけていました。二代目の代で加工専門へと舵を切り、皮むきサメ、イワシの丸干し、鰹節などさまざまな加工を経て、現在の干物づくりに行き着きました。
いちばん好きな魚は鯵(アジ)、干物屋だけどアジフライ。
以前は“鯵の開き派”だった鈴木さん。ある日、地元で揚がったアジを自分で捌いてアジフライにしてみたら、その美味しさに衝撃を受けたそう。事務所にはギターやピアノ、ドラムがずらり。たまに3人のお子さんたちと演奏するのだとか。加工場の前のアスファルトにチョークで描かれた絵も微笑ましい。ここには、仕事と家族の暮らしがともにあります。
干物離れへの危機感、骨なし加工への挑戦
鈴木さんは大学卒業後に、日本全国の魚を学ぶため、築地市場で修行を経て家業へ。創業以来「丁寧な手仕事」「素材の味」を合言葉に、地元いわきの水産資源を活かした干物製造に取り組んできました。
しかし干物には課題もあります。干物は食べ方が難しい。手軽なようで骨が多く、子どもがいる家庭では敬遠されがち。せっかく地元にはおいしい魚があるのに、このままでは食卓から遠ざかってしまう——。
ここで揚がる魚はおいしい、だから食べてほしい。鈴木さんはその一心で、骨を気にせず食べられる商品作りに挑みました。こうなったら、カタチも味もとことん食べやすく!パクパク食べられる魚料理を目指し、子どもたちの反応を見ながら試作を繰り返しました。そして、いわきを代表するメヒカリとカレイ、近年いわきに揚がるようになったカマスの3種を、骨なしの唐揚げ用に加工することに。
忙しくなったら、シャカシャカ要員を増やさないと(笑)
1匹ずつウロコを落とし、頭と腹わたを取り、中骨を抜いてフィレ状に。さらに粉付け——。すべて家庭調理と同じ工程を、手作業で行います。気の遠くなるような手間にもかかわらず「もっと忙しくなったら、粉付け担当(シャカシャカ要員)を増やさないとですね」と笑う鈴木さん。とにかく魚を食べてもらいたい”。その真っ直ぐな思いが、丁寧な加工ににじみ出ています。
シンプルな味付けこそ
新商品の味付けは薄味にこだわりました。家族の高血圧をきっかけに、薄味で育った鈴木さんには、市販品の味付けが過剰に感じるのでした。魚の旨味を引き立てるために、あえて薄味に。だからこそ塩は慎重に選び抜き、塩味だけでなく甘味を感じる「天日湖塩」を使っています。からりと揚がった唐揚げを試食させてもらうと、3種の白身魚の味も個性もしっかり感じられて、シンプルな味付けこそが重要であることがわかります。
子どもからは素直な反応が返ってきますからね。
若い頃は味にこだわるよりも、たくさん作ることが優先だったなと、今になって思います。子どもが産まれてからは考え方も変わって、改めて丁寧な手仕事が大切だと強く思うようになりました。子どもが食べておいしいって言う魚って、どんなものなんだろう、今ではこれが基準です。
カネキュウの干物づくりは、技術でも歴史も大事だけど、いつも家族の食卓にある“やさしい味”が原点。いわきの魚を、もっと身近に、もっと楽しく。鈴木さんのつくる一品一品には、その願いが静かに宿っています。