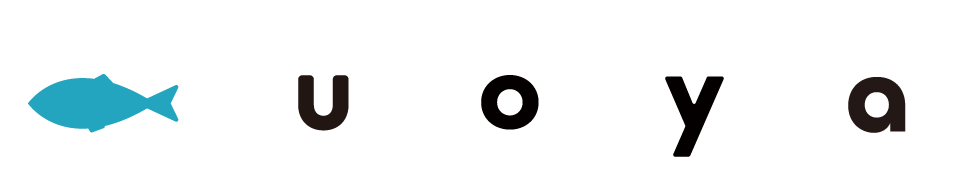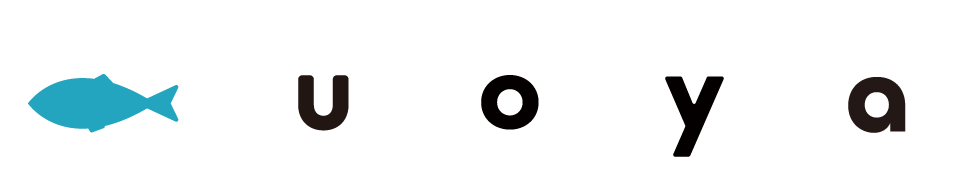工場の前から始まっている
福島県いわき市江名町。カネセン水産の加工場に立つと、まず視界に入るのは、商品が並ぶ一角です。冷凍のタコ、青さのり、魚介だし。ここでは「作る」と「売る」が分断されていない。加工場の前で、もう買い物が始まっています。創業は昭和25年。祖父の代に始まり、坂本剛士さんで三代目。もともとはタコ専門ではなく、この地域で水揚げされた魚を加工するところから始まったといいます。本格的にタコ加工へ舵を切ったのは父の代。関西から茨城へと伝わった蛸の加工技術を学び、この町に根づかせてきました。
福島のタコって、ちゃんと言われるようにしたい。
その言葉は、過去を誇るためではなく、これからの話のことを話しているように聞こえました。
震災を越えて、原料を地元に戻した
お父さんの代には、アフリカ産のタコが大量に日本へ入ってきた時代がありました。柔らかく、甘みもある。坂本さん自身、「決して悪い原料じゃない」と認めます。しかし、資源の減少と世界的な需要の高まりで状況は変わり始めます。そして、東日本大震災。いわき市も大きな被害を受けました。風評被害も重なり、坂本さんは従業員の雇用をいったん止め、妻と二人で再出発するという決断をします。あのとき何を選ぶかで、この先の仕事の形が決まる。そう感じていたと言います。
原料は、もう全部福島県産だけです。
再出発にあたり決めたのは、原料を地元に絞ることでした。水揚げは少なく、商売として成立するかは分かりません。それでも「ここでやるなら、ここで揚がるものだけでやろう」と腹を括ったそうです。“外の原料は一切使っていない”。言い切る坂本さんの言葉が、この10数年の選択をそのまま表しています。
鮮度は目で買う
カネセン水産の仕入れは、漁師と同じ場所に立つところから始まります。漁協の場で、坂本さん自身が札を入れ、競り落とす。真蛸は生きたまま水揚げされることも多く、状態はその場で判断できます。
生の状態で揚がるから、自分の目で見て落とせる。鮮度感が違うんです。
扱うタコは主に真蛸(マダコ)と柳蛸(ヤナギダコ)。マダコは冬が旬で、12月頃から2〜3月頃まで。巨大なカゴを海底に落として引き上げる“カゴ漁”で獲ります。壺を沈めて引き上げるような、あのイメージに近いと坂本さんは言います。一方のヤナギダコは底引き漁。沖合いの漁場で、メヒカリなどと同じように網で一気に引き上げるスタイルです。7〜8月は休漁で、春(4〜6月)と秋(9〜11月)が主なシーズン。量が取れる時期に原料をストックして、年間を通して提供できるように整えるのも仕事のうちです。
福島のタコを日常へ
子どもは魚が苦手でも、たこ焼きは食べる。
原料が高く、資源も不安定な時代だからこそ、「どう食べてもらうか」を考え続けています。販路も市場中心から、道の駅や物産館、対面販売へ。最初は見向きもされなかった商品が、朝市やマルシェで少しずつ知られ、いまでは工場まで直接買いに来る人も増えています。「タコというと明石や三陸のイメージが強い。福島はまだ弱い。」坂本さんはそう話します。だからこそ、味付けや形を工夫して、納得してもらえる“福島のタコ”を作っていきたい。タコは骨がないから食べやすい。魚食の入口になれる力がある——現場の実感が言葉の端々ににじみます。
漁師から仕入れ、目で選び、手で整え、食卓へ近づける。
福島のタコが、特別なものではなく、いつものごはんになる日を思い描きながら。
坂本さんの仕事は今日も、加工場の中で静かに続いています。