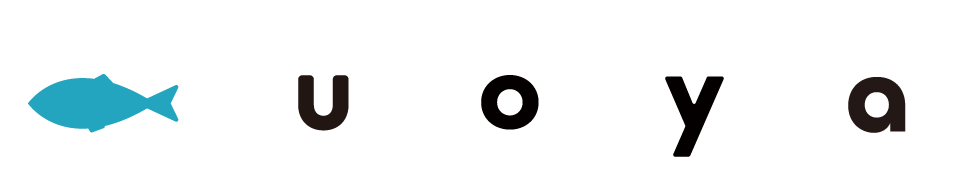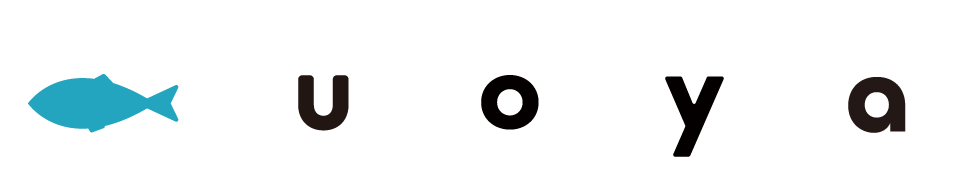目の前が海という場所
茨城県大洗町。遠浅の海と広い砂浜が続く大洗サンビーチは、夏になると多くの人でにぎわう場所です。そこから2キロほど内陸に入ると、水産加工を手がける兼多水産の社屋が建っています。すぐ裏手には涸沼川が流れ、朝にはシジミ漁の船が何艘も行き交います。海と川の気配が、今も日常のすぐそばにある土地だ。
今朝も川でシジミをかいてましたよ。
そう教えてくれたのは、代表の関根貴志さん。兼多水産の創業は昭和36年。大洗港で水揚げされるイワシやシラスの加工から、この会社は始まりました。父が始めた当初は、シラス干しや釜揚げ、イワシの丸干しをすべて天日で仕上げていたそうです。冷凍設備も乾燥機もない時代、干しあがった魚を夕方に市場へ運ぶ。そんな仕事の積み重ねが、会社の原点にあります。
魚がとれない、だから、事業を変えた
昭和40年代になると、大洗の港だけでは仕事が回らなくなりました。安定して生産を続けるため、他の港で揚がる魚も扱うようになり、あわせて冷凍設備などを置ける広い敷地を探して現在の場所へ移転することになります。
昔は船が港に入るとサイレンが鳴って、
それを合図に市場へ向かっていました。
サイレンが聞こえる場所にいなければ、仕事が始まらなかった時代。やがて電話が普及し、港の様子を離れた場所でも把握できるようになると、海のそばにいる理由も変わっていった。技術や環境の変化に合わせて、仕事の形を変える。それは後ろ向きな転換ではなく、続けるための選択でした。
魚がとれなくなったから、やり方を変えた。
それだけのことなんです。
現在は、先代から培われてきた干物づくりの伝統を守りながら、急速冷凍機や真空パック機といった新しい技術も取り入れています。主力は真ホッケ、縞ホッケ、金目鯛の開き干し。生産量の8割を占め、今では福岡や宮城をはじめ、全国のスーパーへと届けられています。
親子二代でつないできた「開き」の技術
工場の中に入ると、作業台の上には真っ赤な金目鯛が積まれ、従業員が一尾ずつ手で魚を開いている。関根さんが魚の開き方を学んだのは、母親からでした。
金目鯛は腹開きに、サンマは頭を残すかぎ開き。魚によって開き方はすべて違う。従業員の高齢化が進むなかで、関根さんは強い危機感を持ちました。「誰か一人だけができる技術」にしてはいけない。そう考え、「全員が一通り、魚を開けるように」と若い世代への指導を続けてきました。見て覚え、手を動かし、感覚で身につける。時間はかかるが、それがいちばん確実な方法だと信じています。
魚の開き方は、教科書じゃなくて、
現場で覚えるものなんですよ。
干しすぎないのが一番おいしい
干物はもともと保存食です。昔は長く保存するため、きつく干す必要がありました。しかし今は、冷蔵や冷凍で流通させることができる。だからこそ、兼多水産では“干しすぎない”製法を選んでいます。
冷風乾燥機を使い、魚の種類ごとに乾燥時間を細かく調整。外の湿度にも影響されるため、10分、15分おきに状態を確認し、水分がほどよく抜けたところで仕上げます。その後、マイナス30℃で急速冷凍し、真空パック包装へ。解凍時のドリップを抑え、家庭でもおいしさを保てるよう工夫を重ねています。
干物は、あまり干さないほうが、
実は身が柔らかくておいしいんです。
最近では、普段あまり見かけない大きな金目鯛を使った干物や、茨城県産の魚を使った商品づくりにも挑戦しています。必要なときに必要な量を確保する難しさはあります。それでも、大洗で生まれ育った者として、少しずつでも地域に貢献していきたい気持ちからだそう。
うちでしかやれないことをやっていきたい。
長年培ってきた技術と、干物づくりへの矜持を胸に。兼多水産は今日も、次の一手を探し続けています。