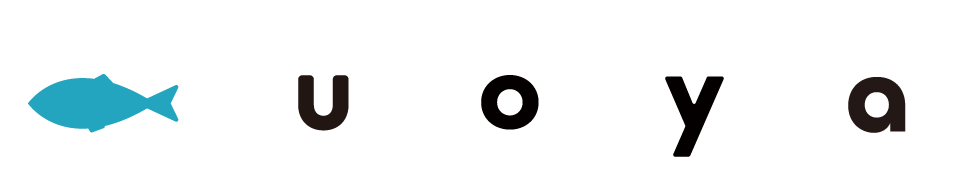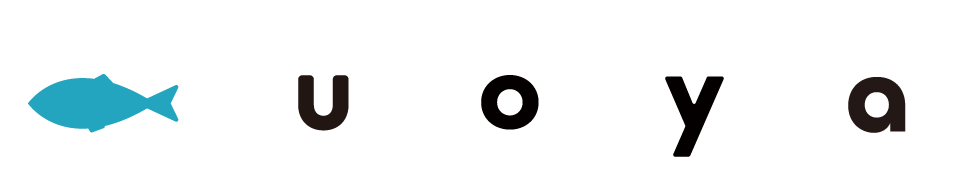かつての観光地、松川浦から再び
福島県相馬市、唯一の潟湖として知られる松川浦。かつては民宿が立ち並び、釣り人や観光客でにぎわう港町でした。 久田則雄さんは、ご両親とともに「あおさ」や「あさり」の養殖を手掛けながら、民宿〈おびすや〉を営んでいました。宿泊客が釣った魚を料理して振る舞うことも多く、食卓には地元の海の幸が並び、常連客との思い出も数えきれないほどです。
朝食の佃煮は甘め。
ピリ辛な佃煮はお酒に合うように作った晩御飯の一品でした。
民宿の料理は、料理上手なお母さんの手作り。 「夜のお膳には、必ず大きな煮魚があって。ホッキご飯やカニピラフなど、どれもおいしかったですね」。 そんな母の味から生まれたのが、〈おびすや〉の佃煮。自家製のあおさを使った佃煮は宿泊客にも評判で、やがてスーパーにも卸すほど人気商品になっていきました。
相馬の漁師を支えた母の佃煮
2011年、東日本大震災がすべてを奪いました。民宿は津波で全壊し、海苔棚も船も網も流され、久田さん一家は廃業を余儀なくされます。 それから数年後、かつての〈おびすや〉の佃煮ラベルを手に、「もう一度、あの味を」と久田さんを訪ねてくる人が現れました。ちょうど試験操業が再開された頃で、漁師仲間の間でも“おびすやの佃煮”を懐かしむ声が上がっていました。
漁に出るとき、お前のうちの佃煮持ってけば他のものがいらないんだ。
底引き船の漁師たちは、海の上での夜食として〈おびすや〉の佃煮を常に持っていました。 その話を聞いた久田さんは、母の味をもう一度届けようと決意します。 素材は地元で揚がる生のいか、にんじん、ごぼう。歯応えを残すため、すべて手作業。
しかし、民宿時代の厨房の火力とは違い、再現は容易ではありません。 試行錯誤の末、震災から10年。〈おびすや〉の佃煮はついに復活しました。「病気で食欲がなかった方から、“この佃煮でご飯が食べられるようになった”という手紙が届いたときは、本当にやってよかったと思いました」と、久田さんは静かに語ります。
復活はみんなの力で
久田さんと奥さんは小学校の同級生。今も二人三脚で佃煮を作っています。 一日に作れる数はわずか80個。すべてが手作業で、作業の分担も“自然体”です。「始めた人が最後まで仕上げる。もう一人は他のことを手伝う。揉めないようにね」と笑います。
松川浦大橋も、海苔棚も、民宿も──
全部、パッケージに描いてもらったんです。
パッケージは、デザインに頭を悩ませていた奥さんは息子さんに相談したのが始まりでした。デザイナーとの出会いが重なり、松川浦の風景と〈おびすや〉の歴史を丁寧に描いたラベルが完成。「私たちだけでは復活させることはできなかった。支えてくれた皆さんのおかげです」。お二人のあたたかい人柄が、そのまま味ににじむような佃煮です。