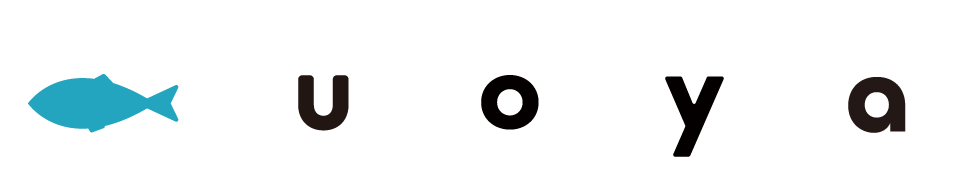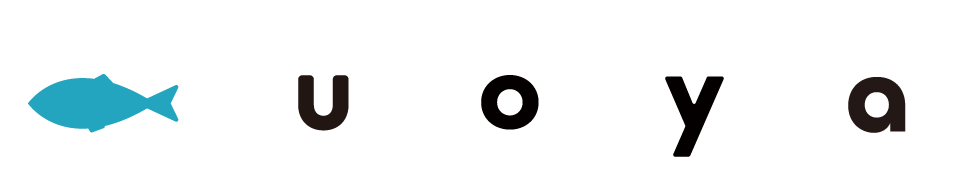失われた場所から、もう一度始める
福島県いわき市で100年以上続く魚屋、株式会社おのざきは、もともと「魚屋さん」としての存在感が強い店です。大正12年に創業し、鮮魚と仕出しを生業にしてきた歴史は、地域の暮らしと重なっています。そんな歴史も、東日本大震災は、その当たり前を一度すべて奪いました。海の近くにあった店舗は津波で流され、目の前にあった寿司屋も消えました。建物にはヒビが入り、残ったものは決して多くなかったそうです。
当時、中学生だった4代目の小野崎雄一さんは、その現場を直接見てはいません。それでも、父や周囲から聞いた話として、唯一残った加工ラインの商品を集中的に東京へ売りに行ったことなど覚えています。小野崎さん自身も、上野駅のコンコースで販売を手伝ったそうです。
「いつか戻る」という感覚は、その頃から揺るぎませんでした。
もう、絶対に戻ると思ってました。
震災は、店を壊しただけではありませんでした。町の風景、文化、人の流れまでも一度リセット。その中で、おのざきは「元に戻す」のではなく、「続けるための形」を探すことになります。
ゼロから立て直す、という選択
小野崎雄一さんが本格的に経営を引き継いだのは2020年。東京からUターンし、4代目として会社の舵を握ったとき、目の前にあったのは厳しい現実でした。資金は足りず、設備は老朽化し、人は次々に辞めていく。社内は荒れ、役員会で「再生しますか、廃業しますか」と問えば、「廃業」に手が挙がるほどでした。
経営会議で“廃業”に手が挙がった時は、正直しんどかったですね。
それでも、小野崎さんは立て直すことをあきらめませんでした。補助金に頼る体質から脱却し、自分たちの力で次の柱をつくる。そのためにまずやったのは、オンライン販売への注力でした。コロナ禍をきっかけにECを強化し、商品開発にも本腰を入れる。魚の離乳食、常磐ものを使った加工品。ホームページも自ら手を動かして作り、パッケージは地元の若いデザイナーと一緒に形にしていきました。
そんな甲斐もあって、会社は少しずつ筋肉質になっていきました。無理な拡大はしない。だが、次の世代に渡せる形にまでは鍛え上げる。その覚悟が、今のおのざきを支えています。
「常磐もの」で、腹が鳴る世界をつくる
小野崎さんが描いているのは、単なる店舗拡大ではありません。「常磐もの」と聞いただけで、よだれが出る。お腹が鳴る。そんな世界観をつくることです。福島の海は、親潮と黒潮がぶつかる栄養豊富な海。さらに原発事故後、約10年間自由に漁ができなかったことで、資源は驚くほど回復しました。データ上では資源量が7倍近くになっている魚種もあり、身は太く、脂のりもいい。皮肉なことに、震災が海の質を高めた側面もあります。
だが、魚のポテンシャルだけでは文化は広がらない。金沢の寿司が強いのは、「どこで食べても美味しい」というアウトプットがあるからだと言います。常磐ものが弱いのは、そこだと小野崎さんは考えています。だから、魚屋だけでなく飲食店を出し、タッチポイントを増やす。東京の中央線沿線の4駅67店舗に一斉に常磐ものを流通させた企画も、その延長線上にあります。
海外にも目を向けています。シンガポール、そしてドバイへ。安売りはしない。価値を理解してくれる人に適正な価格で売り、雇用を生み、産業として強くする。ただし、地元を置き去りにはしない。地元に根づかせるために、外へ出る。そのバランスを意識しています。
めっちゃ屈伸したんで、あとは高く高く飛ぶだけです。
戻す世代ではなく、つくり直す世代として。
おのざきは今、次の100年に向けて助走を終えたところに立っています。